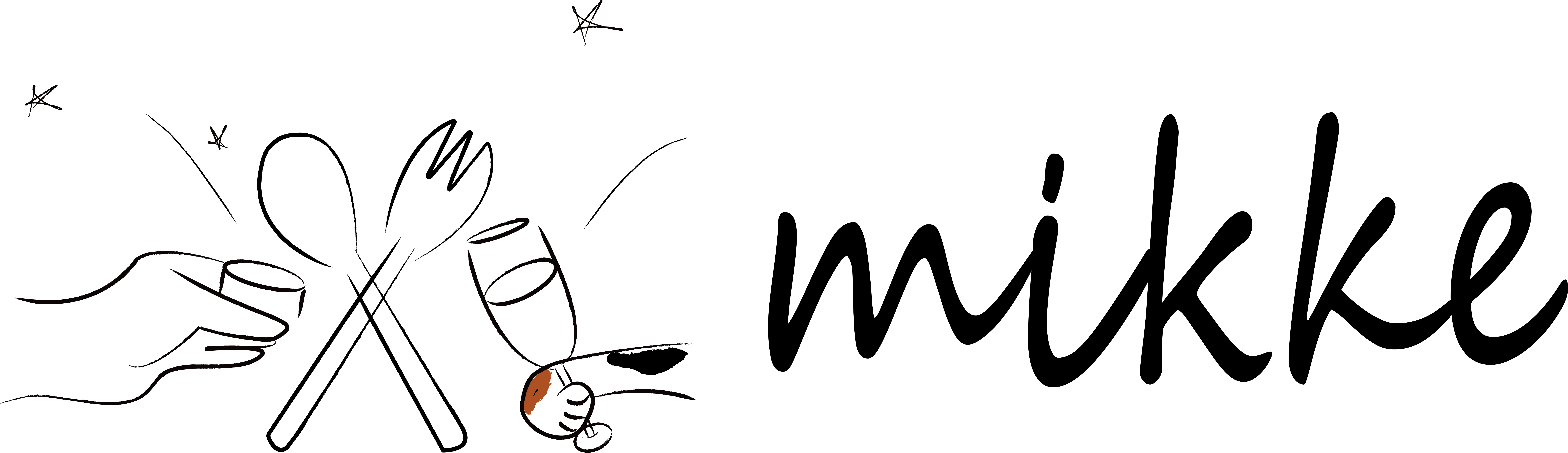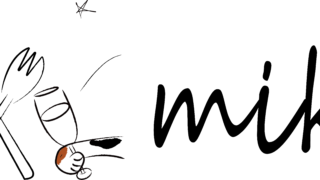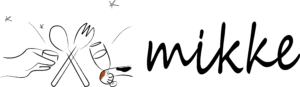お酒が弱い人と弱い人がいるのはなぜ?
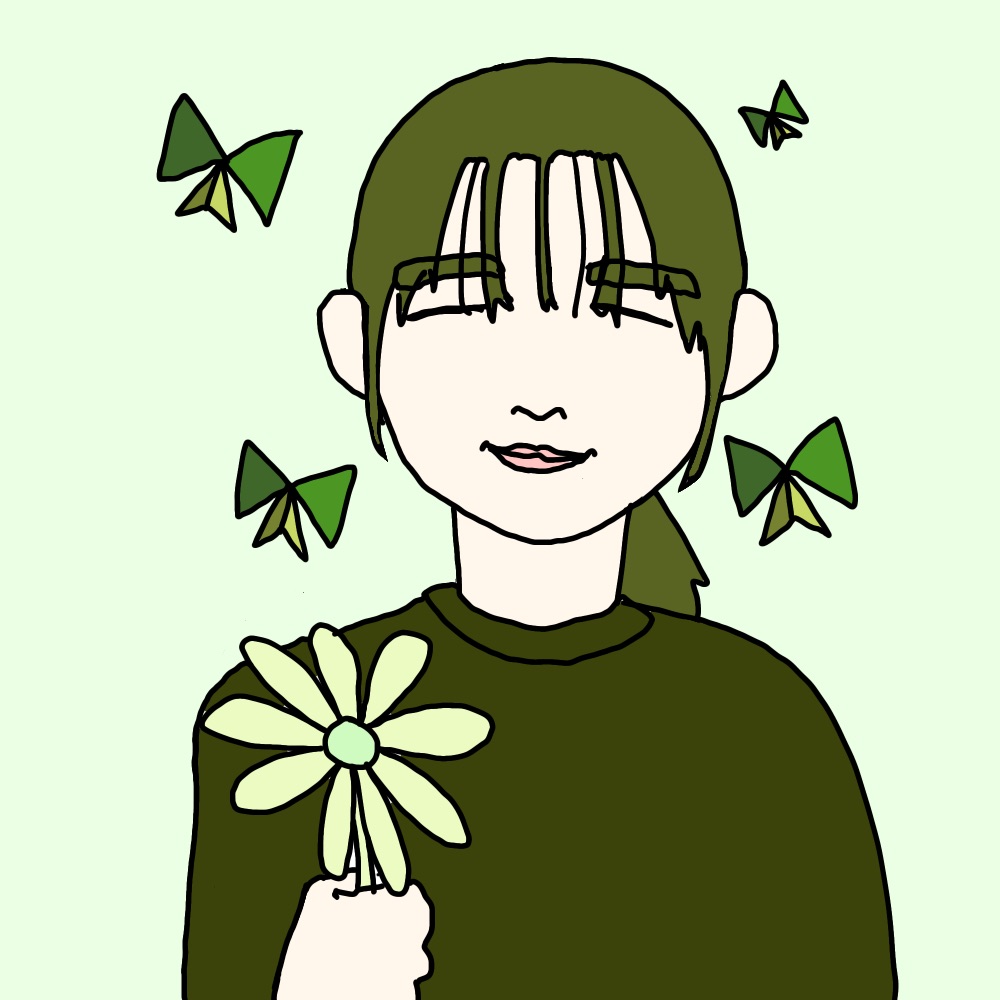
皆さん、はじめまして。mikkeのデザイナー緑茶割りです。
今回は、なぜお酒に弱い人と強い人がいるのか、私なりに解明していく回にしようと思います。
それではよろしくお願いします。
アルコール分解の仕組み
アルコールが排出されるまで
体内に入ったアルコールは20%が胃で、80%が小腸で吸収されます。
そして血管を通って肝臓に集められ、酵素によって分解されます。その酵素がADH(アルコール脱水素酵素)です。
ADHによってアルコールはアセトアルデヒドに分解されます。次にALDH(アセトアルデヒド脱水素酵素)によって酢酸に分解されます。
その後、酢酸は全身に送られ、筋肉や脂肪組織で二酸化炭素と水に分解され、呼気や尿となって体外へ排出されます。
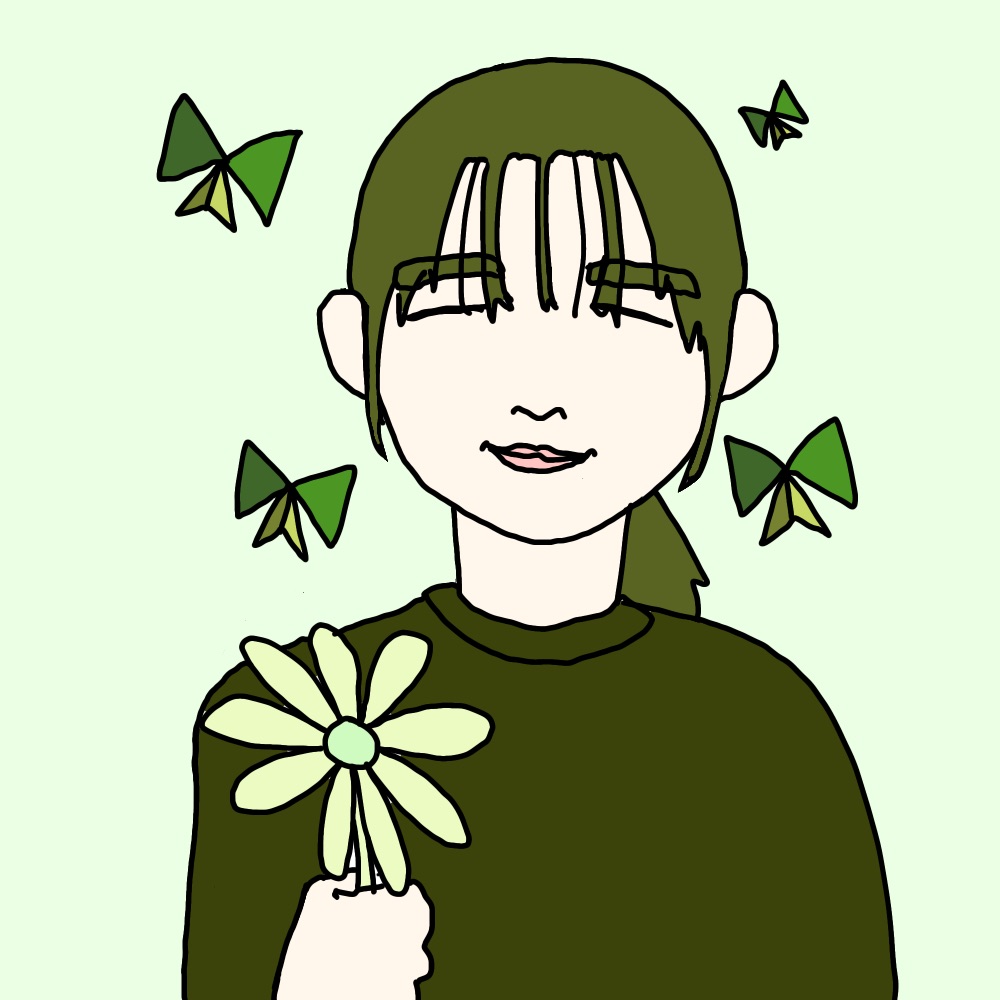
いきなりADHとかALDHとか酢酸とか言われてもピンと来ないのは私だけでしょうか。
これをより詳しく調べていきます。
酵素について
酵素は基質と呼ばれる特定の分子と結合し、反応を進行させます。このとき、酵素の活性部位が基質と適合する形状を持っているため、特定の物質にのみ反応を促進します。酵素はタンパク質であり、たった20種類のアミノ酸がペプチド結合により数百~数千個連なってできています。
主な種類
- 消化酵素: 食物を分解し、栄養素を吸収しやすい形に変えます。例: アミラーゼ(デンプン分解)、ペプシン(タンパク質分解)、リパーゼ(脂肪分解)。
- 代謝酵素: 体内の代謝反応を調整し、エネルギー生産や老廃物の除去をサポートします。例: アルコールデヒドロゲナーゼ(アルコール分解)、チロシナーゼ(メラニン生成)。生物体は、主に水素、酸素、炭素、窒素などの元素で構成されており、人体の細胞内では休むことなく原子や分子の組み換えが行われています。これを新陳代謝といいます。
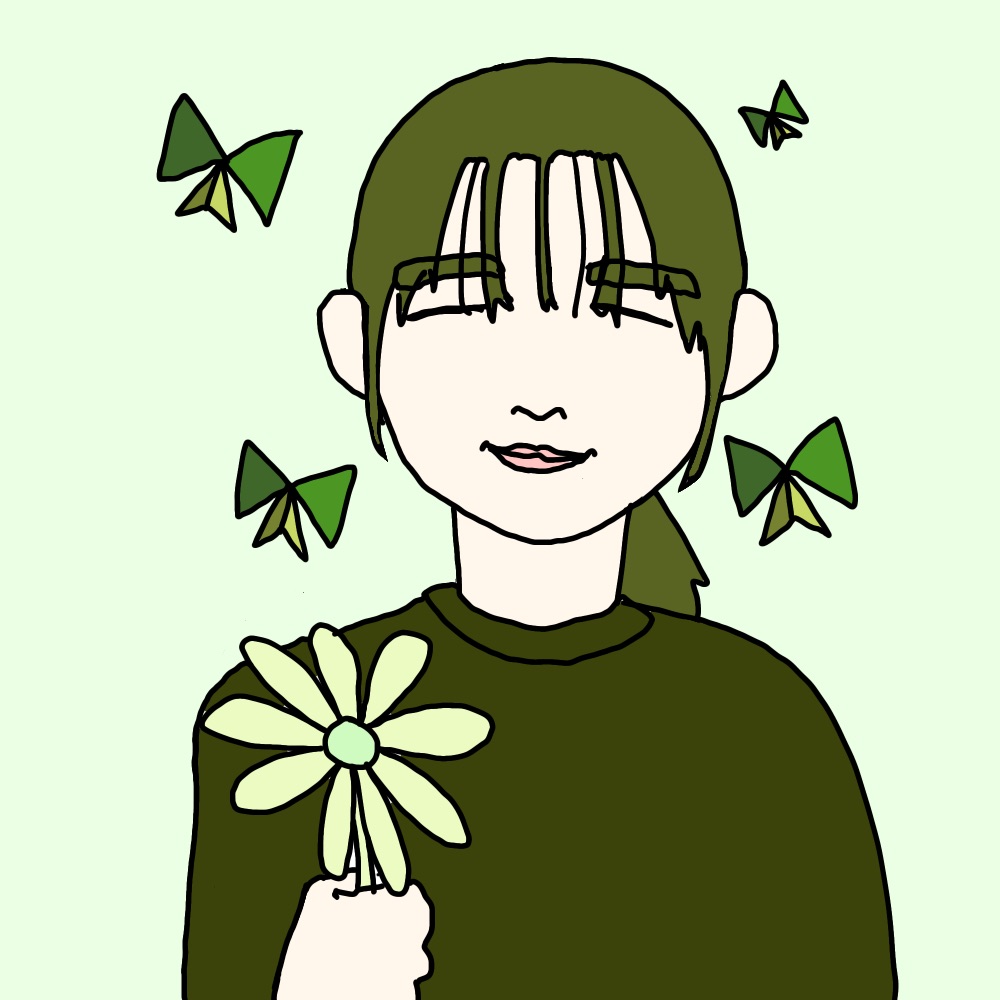
アルコール分解は代謝酵素によるものなんですね、代謝酵素の働きとして解毒とあったのでそれに該当するんですかね。
あと体内酵素(元から人間の体にある酵素)と体外(外から取り入れる酵素)があるみたいです。
なんとなく酵素サプリとかジュースとか取り入れたくなりました。
ADHとALDH

ADHとアセトアルデヒド(一次代謝)
エチルアルコール(エタノール)が含まれる飲料を一般的には“お酒”と呼んでいます。エチルアルコールの化学式は「C2H5OH」。
このエチルアルコールは、体の中の特に肝臓で分解されるのですが、その過程で”酸化”されると“アセトアルデヒド(CH3CHO)”になります。
ADH(アルコール脱水素酵素)はそのはたらきを加速する触媒として働き、反応の速度を高めます。
酵素自体は反応後も変化せず、再利用可能です。
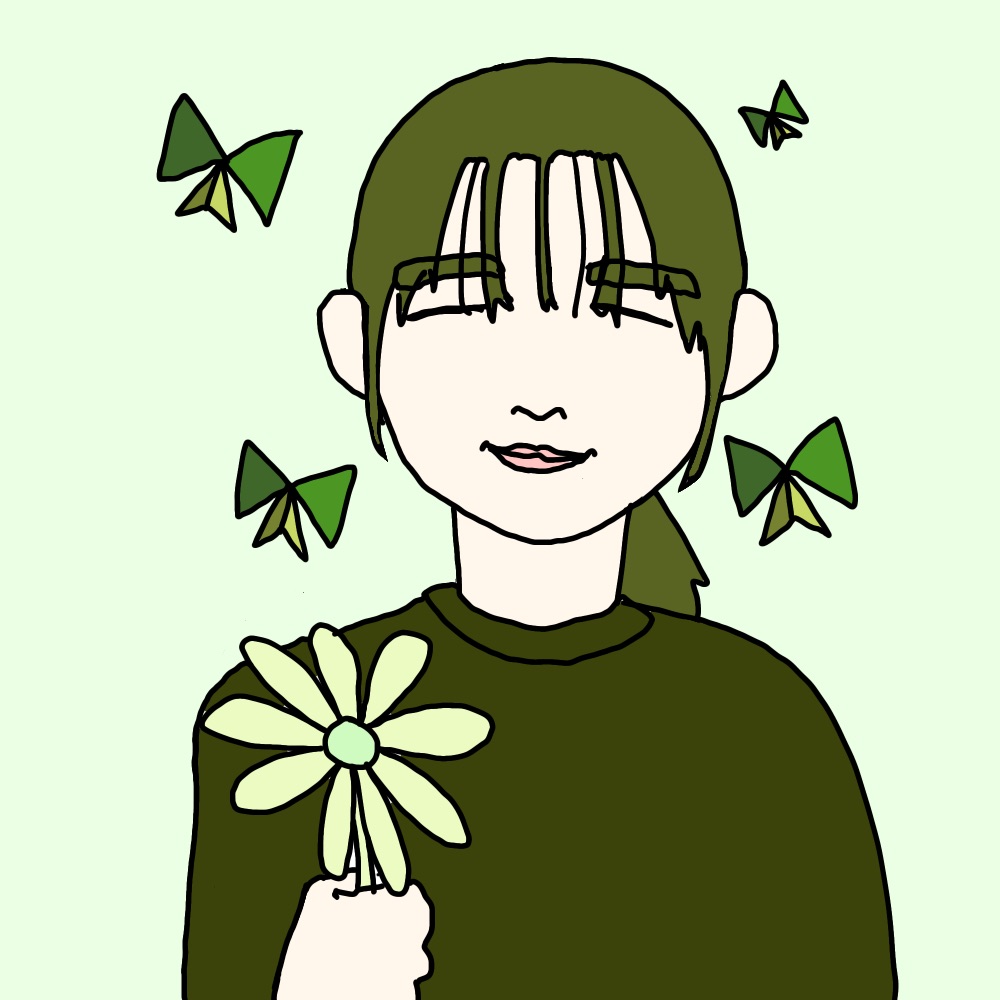
化学式はよくわかりませんがADHによってエチルアルコールが水素を失った(酸化した)姿がアセトアルデヒドということですね。
ALDHとアセトアルデヒド(二次代謝)
アセトアルデヒドは非常に反応性の高い化合物で、細胞や組織にダメージを与えやすい毒性を持っています。
頭痛、吐き気、動悸,お酒を飲んで顔が赤くなるのは、アセトアルデヒドの血管拡張作用からです。
アセトアルデヒド脱水素酵素(ALDH)という酵素によって毒であるアセトアルデヒド(CH3CHO)を”酸化”させ無害な酢酸(CH3COOH)へと変化させます。
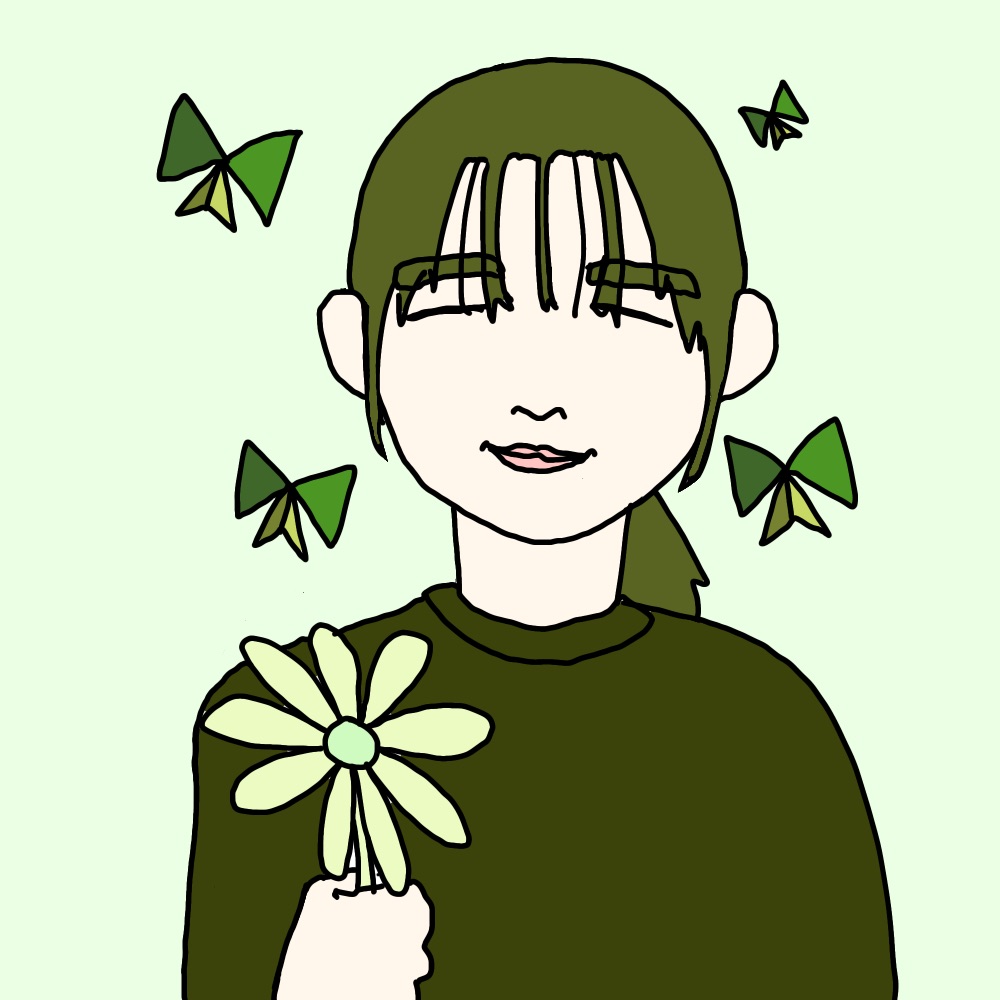
アセトアルデヒドが酔う原因ぽいですね。
酢酸はアセテート繊維や写真の不燃性フィルムのなどの工業原料として使われてるみたいです。
人間の体ってすごいな~
遺伝性
遺伝子の基本
人間には複数のADH遺伝子(例えば、ADH1、ADH2、ADH3など)があり、これらの遺伝子のバリエーションは民族や個人によって異なります。遺伝子は、体内で特定のタンパク質を作るための設計図のようなもので、これらの設計図は親から子へと受け継がれます。ADHの遺伝子もその一部で、これにより個々人のADH酵素の働きが決まります。
遺伝的変異
特定の遺伝的変異により、ADHの活性が高い人もいれば、低い人もいます。例えば、ADH1B2という変異は、アルコールの分解が非常に速い酵素を作り出し、主に東アジア人に多く見られます。一方、ALDH22という変異は、アセトアルデヒドの分解を遅くする酵素を作り出し、これも東アジア人に多く見られます。このような遺伝的変異により、お酒の強さや酔いやすさに大きな差が出ます。
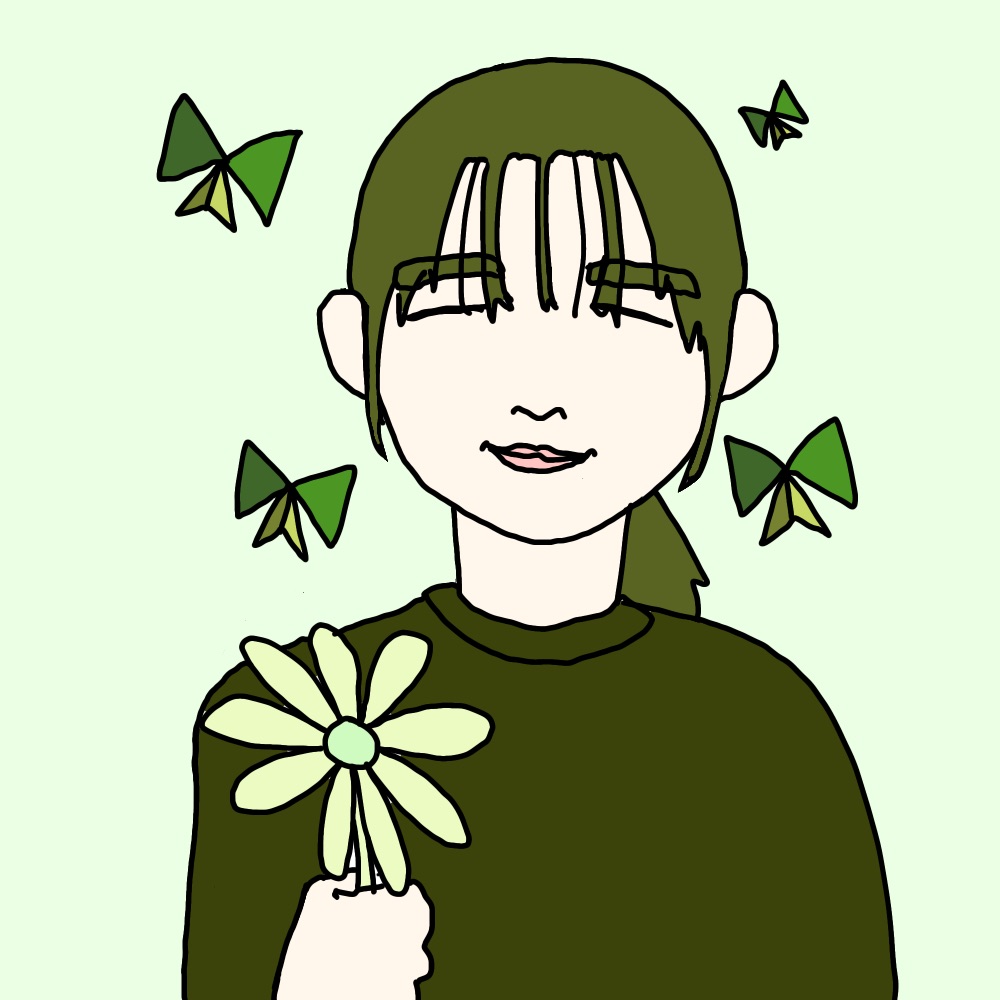
お酒に酔うってADHのはたらきが追いつかなくなって毒素が排出されないことによって起きるんですね。
歴史的にお酒を飲む文化がある地域では、アルコール分解酵素の活性が高い人が生き残って子孫を残してるから地域的にお酒に強いという現象が起きるみたいです。
体重と体脂肪
BAC(血中アルコール濃度)
血中アルコール濃度 (BAC) とは、血液中のアルコール濃度を示すものです。具体的には、アルコールのミリグラム数を血液100ミリリットルあたりの数値で示します。体重が多いとアルコールが体内で希釈されるため、影響が軽減されます。
血液量
体重が多い人と少ない人の血液量が異なるのは、体内の総体積に比例しているからです。基本的に、体が大きくなると、体内で必要とされる血液の量も増えます。
- 体内の細胞数: 体が大きいほど、より多くの細胞が存在し、その全てに酸素や栄養を運ぶために血液が必要です。
- 組織の量: 体重が多い人は、筋肉や脂肪の量も多い場合が多く、それぞれの組織に血液を供給する必要があります。
- 循環系の負担: 体重が多いと、心臓や血管に対する負担も大きくなるため、血液量が増加し、効率的に酸素や栄養を運ぶ役割を果たします。
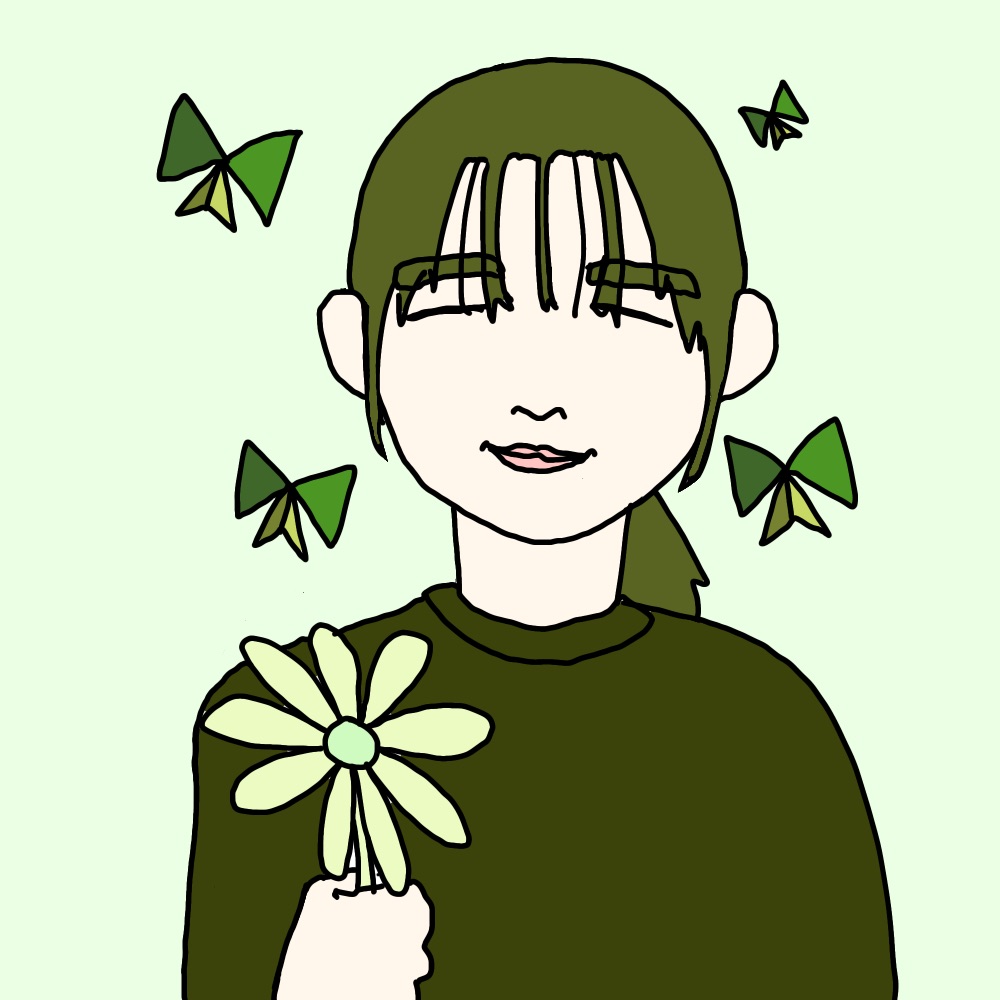
体重が多いと痩せてる人に比べて血液の総量が多くなって血液のアルコール濃度が低くなるから酔いにくいんですね。
学生時代に友人数人と献血に行って『あなたの体は献血に最適です』と言われたことを思い出します。
その後しっかり400mlの血液を収めてきました。
性別の違い
女性は男性に比べ、平均して肝臓の酵素活性が低いため、同じ量のアルコールでも酔いやすいです。
- エストロゲン: 女性ホルモンであるエストロゲンは、アルコール代謝に影響を与えます。エストロゲンは肝臓の酵素活性を抑制する効果があるため、アルコールの分解が遅くなります。
- 月経周期: 月経周期に伴うホルモンの変動も、アルコール代謝に影響を与えることがあります。月経前は特に酵素活性が低下しやすいです。
エストロゲン
エストロゲンが特定の酵素を抑制することで、ホルモンバランスを整える役割を果たします。エストロゲンは月経周期の調整や妊娠の準備に関わり、子宮内膜を厚くし、受精卵が着床しやすくする働きがあたえられています、ゆえに男性に比べて女性はエストロゲンが多いです。
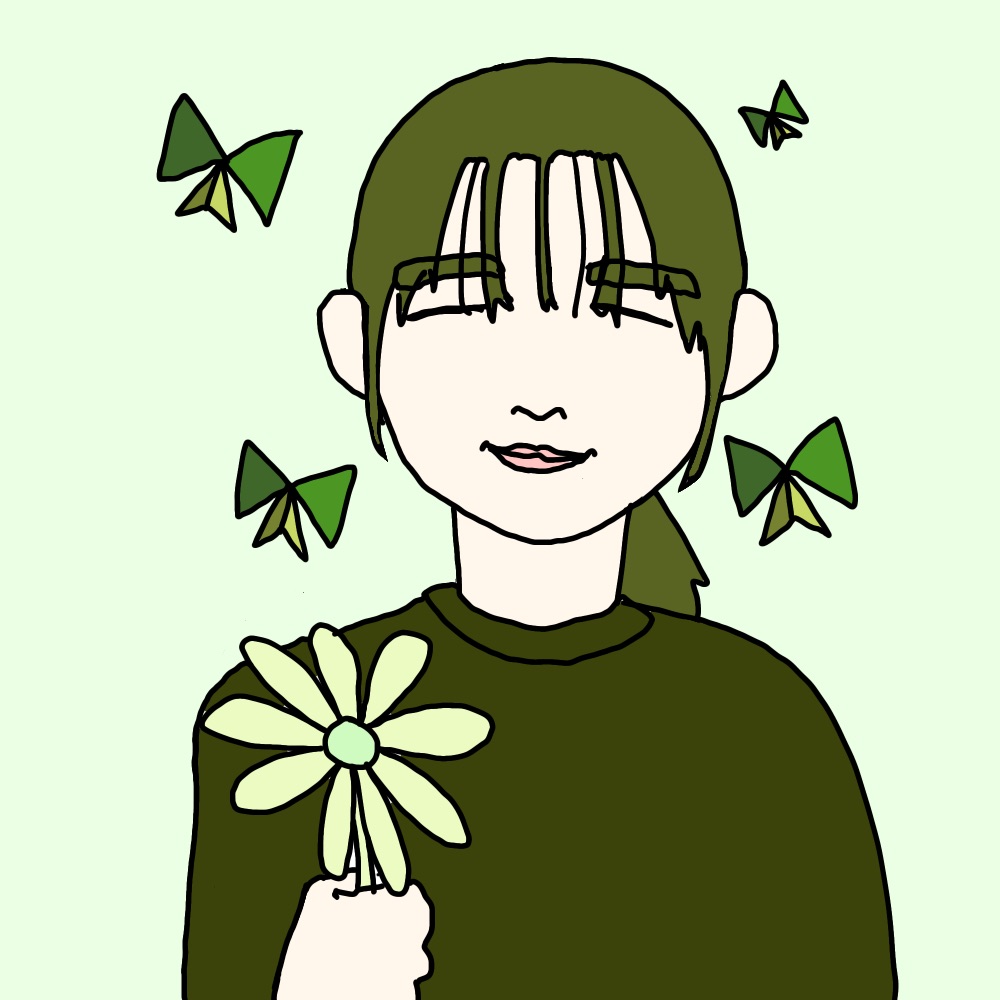
エストロゲンがホルモンバランスを整えてくれる代わりに付随する作用で酵素のはたらきが低下して代謝が遅くなるわけですね。
エストロゲンのはたらきとして①酵素の発生を抑制 ②酵素の分解促進 ③基礎と酵素の結合阻害があるみたいなんですけど酵素の敵すぎませんか?
お酒は慣れると酔わなくなる
お酒の耐性をつけるメカニズム
酵素の増加
繰り返しアルコールを摂取すると、アルコールデヒドロゲナーゼ(ADH)やアルデヒドデヒドロゲナーゼ(ALDH)の生成が増えます。
これにより、アルコールの分解が速くなり、同じ量のアルコールでも酔いにくくなります。
神経系の適応
- 受容体の変化:アルコールは脳内の神経伝達物質の活動を抑制します。長期間のアルコール摂取により、神経細胞の受容体の数や感受性が変化し、アルコールの影響を受けにくくなります。
- 神経伝達物質のバランス:アルコールは抑制性の神経伝達物質を強化し、興奮性のグルタミン酸の効果を抑制します。長期間の摂取により、脳はバランスを取るためにこれらの神経伝達物質のレベルを調整し、アルコールの効果を軽減します。
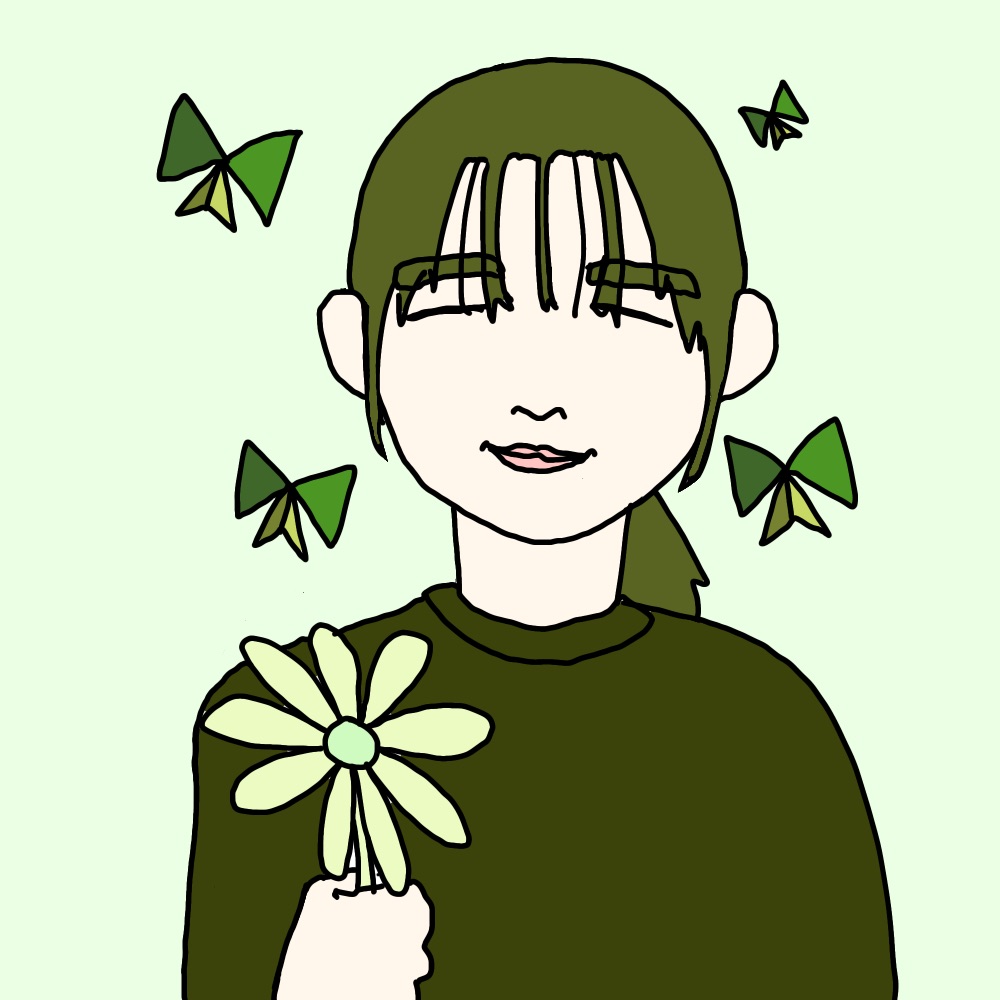
アルコールの作用をおさえるために細胞たちの形態が変わっていくなんて感動です。
細胞たちはなんて健気なんでしょう。
すきっ腹は酔いやすい
すきっ腹は酔いやすい
すきっ腹が酔いやすくなる要素
吸収が速くなる
- 胃の空っぽ: 空腹の時、胃には食べ物がないため、アルコールが胃を通過して小腸に早く届く。小腸はアルコールを吸収する主要な場所だから、結果としてアルコールが急速に血流に乗る。
- 血中アルコール濃度の上昇: 急速な吸収は血中アルコール濃度(BAC)の急激な上昇を引き起こし、短時間で酔いが回る。
胃の刺激
- 胃壁への影響: 食べ物がない状態では、アルコールが直接胃の壁を刺激し、胃腸の不快感や吐き気を引き起こすことで酔った感覚になる。
血糖値の変動
- 低血糖リスク: アルコールは肝臓でのグルコース(血糖)生成を抑制するため、空腹時には血糖値がさらに低下しやすくなる。
低血糖は気分の悪化や混乱を引き起こす。
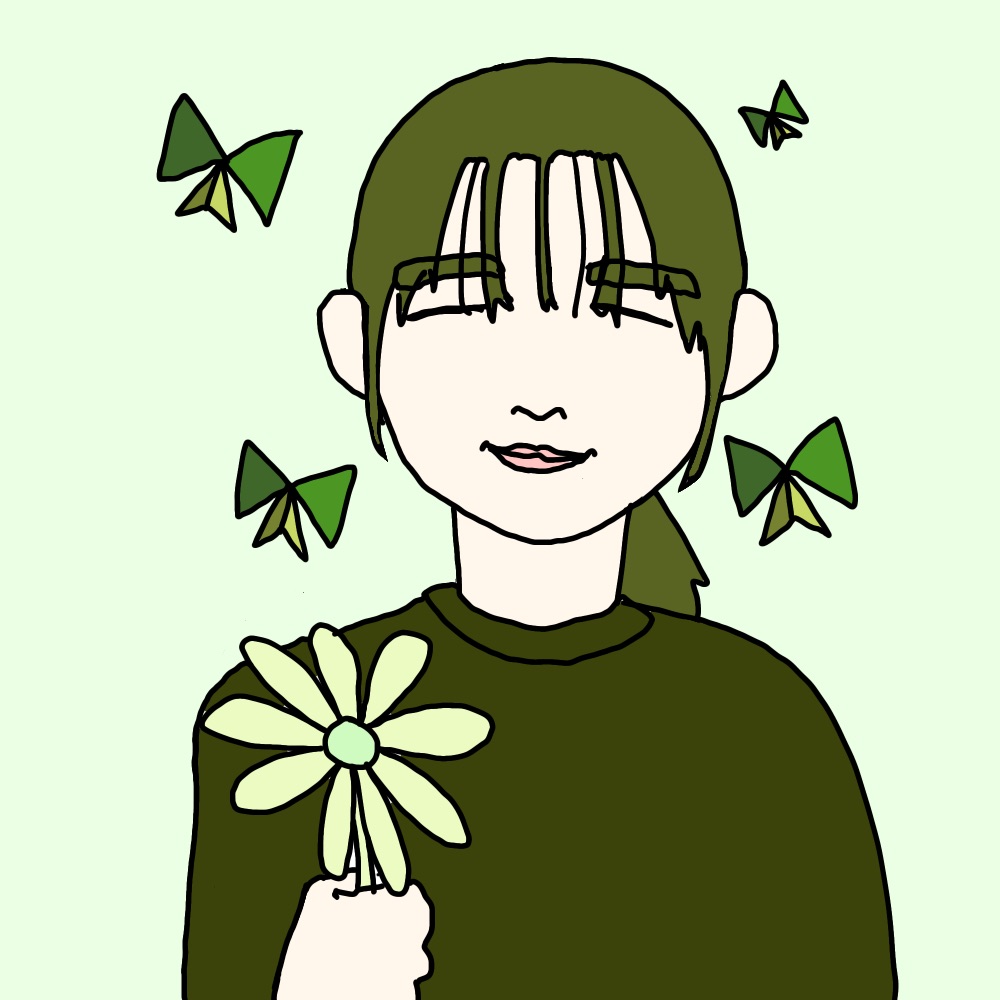
当たり前ではありますが酔っぱらうという現象は色々な症状が合わさって『酔う』という1つの表現になっているんですね。
お酒のアテといえば私は砂肝ですね、コリコリ食感がたまりません。
コメント欄で皆さんの好きなおつまみを教えてください。
チェイサーは何のためにあるの
チェイサーの役割
味のリセット
- 口直し: 強いお酒を飲んだ後に飲むことで、口の中の味をリセットし、次の一杯をより楽しむため。
アルコールの濃度調整
- アルコールの緩和: 強いアルコールの後に水やソフトドリンクを飲むことで、体内でのアルコール濃度を緩和し、酔いの進行を遅らせる。
脱水症状の予防
- 水分補給: アルコールは抗利尿ホルモン分泌を抑制するため、腎臓からの水分再吸収が減少し、尿の排出が増加するため脱水になりやすい。なので水分を補給することで脱水症状を予防する必要がある。
アルコールの代謝を助ける
- 肝臓の負担軽減: アルコールからアセトアルデヒドに分解する過程で十分な水分があると酵素の働きが促進され、アルコールの代謝がスムーズになります。
- 毒素の排出: 水分が十分に取られていると、尿の生成が促進され、アルコールやその代謝物が速やかに体外に排出されます。
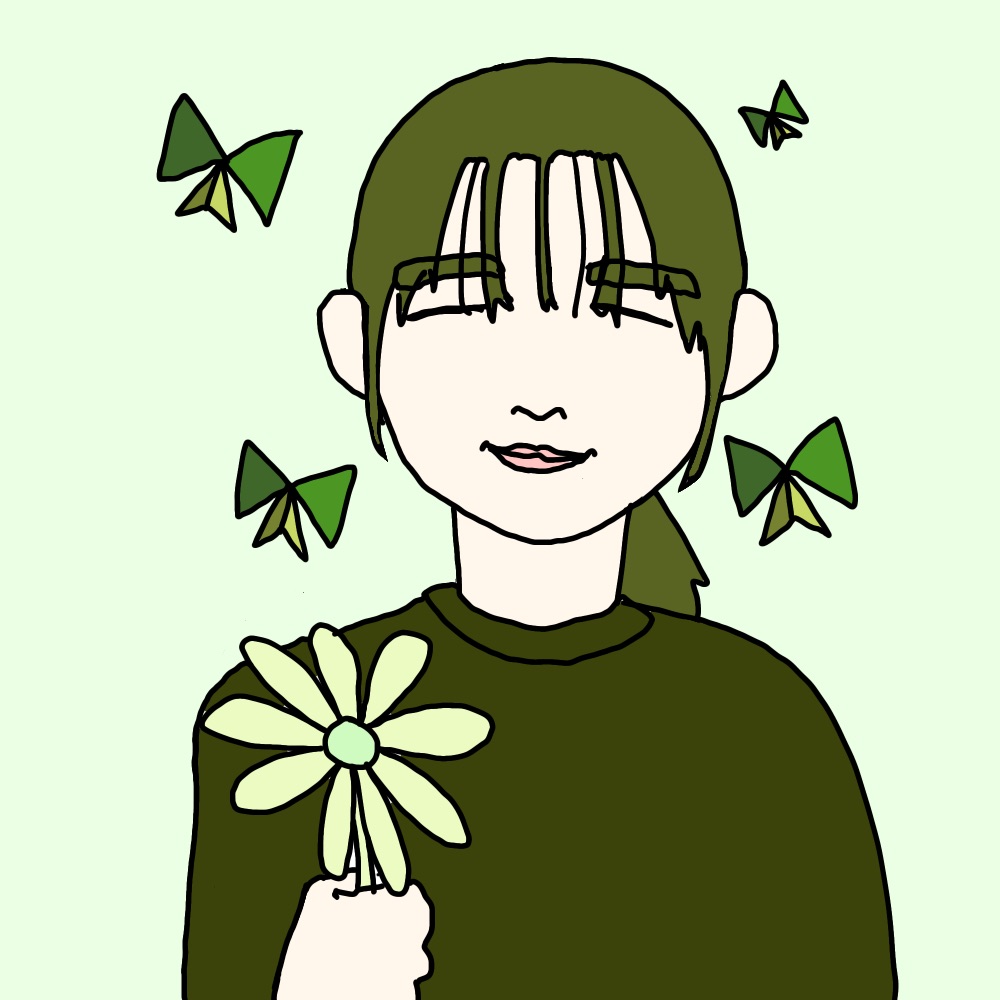
ドラマの飲み会のシーンでよくみる『先輩!一旦ちょっとお水のみましょう』にはちゃんと意味があったんですね。
チェイサーは英語で『chase』追う・追跡するという意味があるそうです、かっこいいです。
この記事でお酒が強い人、弱い人がいる理由がとてもよくわかりましたね。
お酒は美味しいです、しかし、飲みすぎはよくありません。
なので皆さんも正しいお酒の習慣を身に着けて楽しんでくださいね。